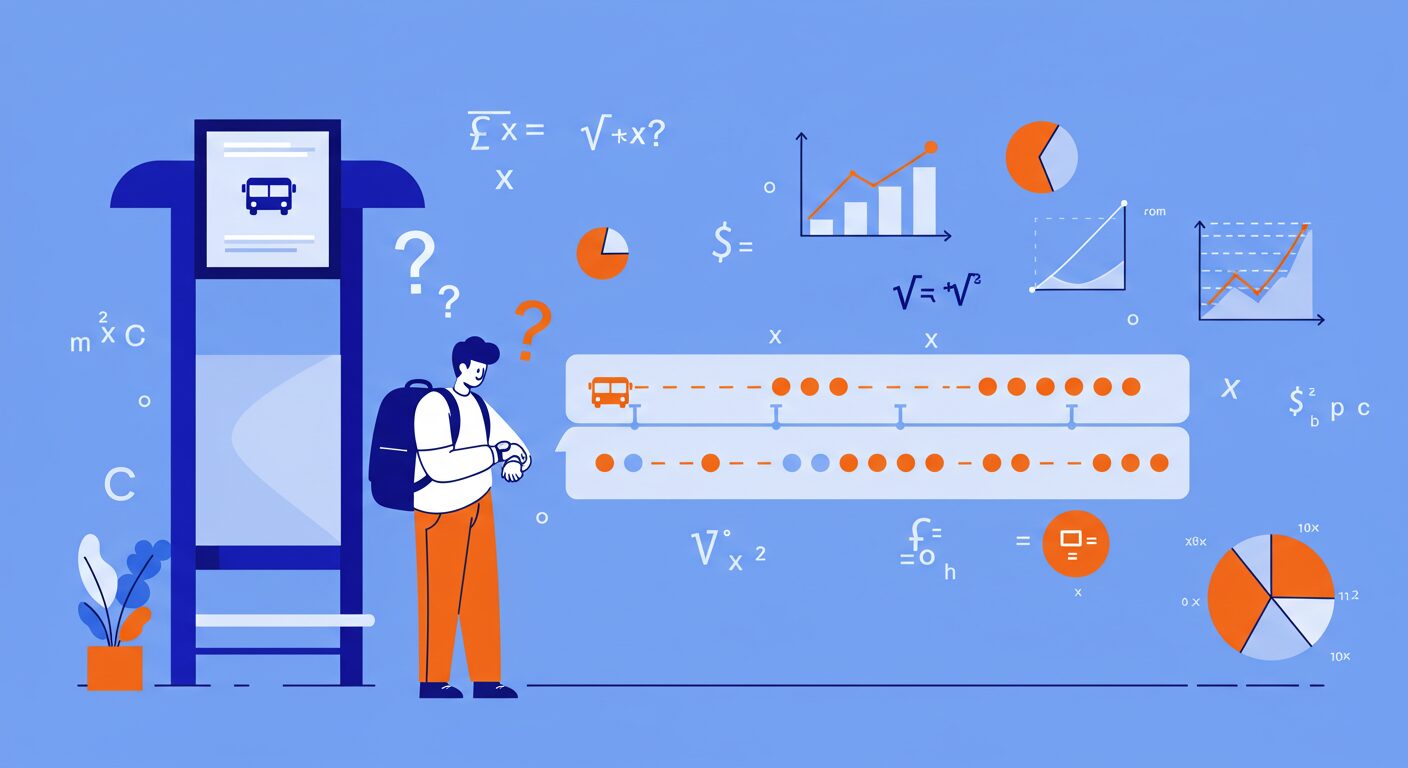TL;DR(30秒で要点)
ランダムな時刻に観測すると、長い間隔に当たりやすいため、体感する間隔・待ち時間は平均より長くなりがち。これが検査パラドックス(Inspection Paradox)。
数式で言うと、平均間隔を m、変動係数を CV とすると、
観測される平均間隔 = m·(1 + CV²)、平均待ち時間 = ½·m·(1 + CV²)。
はじめに
「ダイヤは10分ごとなのに、気づけば15分待ってる…」
——それ、錯覚ではなく“統計の性質”です。
毎日の通勤で「いつも待たされる」と感じるのは、単なる運の悪さではありません。原因のひとつが検査パラドックス。本稿では、直感→式→ミニ実験の順で、なぜ“長く待つ側に偏る”のかをスッキリ解説します。
検査パラドックスとは?(超要約)
ランダムな時点で観測すると、長い区間ほど出会いやすいため、体感する間隔は母集団の平均より長くなる——これが検査パラドックスです。
式だけ覚える版:
平均間隔 m = E[X]、分散 Var[X]、変動係数 CV = SD[X]/m とすると、
観測される平均間隔 = E[X²]/E[X] = m·(1 + CV²)
平均待ち時間 = E[X²]/(2E[X]) = ½·m·(1 + CV²)
直感でわかる:なぜ長い間隔に当たりやすい?
時間軸上に「5分区間」と「15分区間」が半々で並ぶとします。あなたがランダムな時刻に到着するなら、物理的に長い区間に着地する確率が高い(この例では3倍)ため、体験する平均間隔は10分より長くなります。
| 間隔の分布(例) | 母平均間隔 m | 観測される平均間隔 | 平均待ち時間 |
|---|---|---|---|
| 一定10分(CV=0) | 10分 | 10分 | 5分 |
| 5分/15分が各50%(CV=0.5) | 10分 | 12.5分 | 6.25分 |
| 指数分布(CV=1) | 10分 | 20分 | 10分 |
ポイント:ダイヤが一定なら“平均5分待ち”ですが、ばらつき(CV)が大きいほど、あなたの体感は伸びます。
数式でつかむ“体感が伸びる”理由
# 直感の導出(要点だけ)
E[X²] = Var[X] + (E[X])² = m²·(CV² + 1)
観測される平均間隔 = E[X²]/E[X] = m·(1 + CV²)
平均待ち時間 = ½·E[X²]/E[X] = ½·m·(1 + CV²)指数分布(発車にランダム性が大きい)だとどうなる?
指数分布は CV=1 なので、観測される平均間隔は 2m、平均待ち時間は m。
「平均10分運行なのに、いつも10分くらい待つ」のは、ダイヤに揺らぎがあるときに自然と起こります。
1分でできるミニ実験(シミュレーション)
# Python(Colab可):検査パラドックスを可視化
import numpy as np
np.random.seed(42)
# 例1:5分/15分が半々
n = 100000
intervals = np.random.choice([5,15], size=n)
m = intervals.mean()
# ランダムな時刻に到着 → 区間長で重み付けされた確率で区間に当たる
weights = intervals / intervals.sum()
observed_interval = np.random.choice(intervals, size=10000, p=weights).mean()
mean_wait = observed_interval / 2 # 無記憶でない一般の更新過程でも平均待ちは観測間隔の半分
print("母平均間隔 m:", m) # ≈10
print("観測される平均間隔:", observed_interval) # ≈12.5
print("平均待ち時間:", mean_wait) # ≈6.25
# 例2:指数分布(CV=1)
intervals = np.random.exponential(scale=10, size=n)
m = intervals.mean()
weights = intervals / intervals.sum()
observed_interval = np.random.choice(intervals, size=10000, p=weights).mean()
mean_wait = observed_interval / 2
print("--- 指数分布 ---")
print("母平均間隔 m:", round(m,2)) # ≈10
print("観測される平均間隔:", round(observed_interval,2)) # ≈20
print("平均待ち時間:", round(mean_wait,2)) # ≈10実世界での“あるある”
- ネット回線:快適な時間は短く、遅い時間に遭遇しがち。
- 病院のアンケート:待ち時間が長い患者ほど回答しやすく、統計が“長い側”に寄る。
- コールセンター:長く待った人の不満が目立ち、全体の印象を塗り替える。
対策と心構え(実務と生活のコツ)
- 分布で考える:「平均」だけでなく CV(ばらつき)を意識。CVが大きい路線は待ちが伸びやすい。
- リアルタイム情報を活用:運行アプリで直前の便間隔を見て動く。
- 戦略的にずらす:混雑ピークを避ける/乗り換えで“短い区間”に乗る機会を増やす。
- 評価設計を工夫:顧客満足度は「ランダム時点サンプリング」や「全件ログ」ベースで測る。
1分FAQ
Q. 本当に“いつも遅い”の?
A. ダイヤが一定(CV=0)なら平均待ちは m/2。
ばらつきがあるほど(CV>0)平均待ちは ½·m·(1+CV²) に伸び、“遅く感じる”のは統計的に自然です。
Q. どれくらいばらつくと体感が悪化するの?
A. 目安は CV。例えば m=10分なら
CV=0 → 待ち5分 / CV=0.5 → 6.25分 / CV=1 → 10分。
Q. “遅延”と検査パラドックスの違いは?
A. パラドックスはサンプリングの偏り由来。遅延は運行の実問題。
現実には両方が重なるので、リアルタイム情報の併用が有効です。
まとめ
- ランダム観測では長い区間に当たりやすい(検査パラドックス)。
- 平均間隔 m、変動係数 CV なら、観測間隔は
m·(1+CV²)、平均待ちは½·m·(1+CV²)。 - “平均”だけに頼らず、ばらつきとリアルタイムで賢く動こう。
次に読むなら:「バークソンのパラドックス:選び方が作る“見かけの逆相関”」「シンプソンの逆説:全体と内訳で結論が逆転するとき」